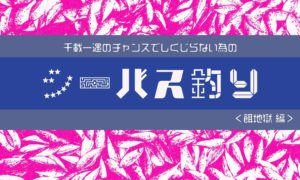AUTHOR

gocho
BURITSU内の愛称は伍長。職業カメラマン。幼少の時「釣りが好き過ぎてヤバい...」と自覚。それ以来、釣りの魅力にハマるのを恐れ自主規制を開始。30年後、規制緩和してから一生の趣味として釣りと向き合う日々を送っている。河川と磯が好きなルアーアングラー。
RELATED SITE


皆さん、こんばんは。
前回のblogはDay Gameに役立つ撮影方法について書かせて頂きました。
今回も実戦で良く見る光景
ナイトゲームのブツ持ち写真に関して書かせて頂こうと思います。
宜しくお願い致します。

Angler:遠藤真一 使用カメラ:Cannon 1Dx/EF24-70mm F2.8L II USM/600EX-RT
夜のブツ持ち写真は、ソルトアングラーにとって避けて通れない道です。。。
そして、コンパクトカメラでの撮影が ほとんどだと思います。
上の参考写真は1眼レフカメラにクリップオンストロボで撮影した写真です。
コンパクトカメラで1眼に近いクオリティーで撮りたい、、、と誰もが願う所。
私も毎回努力しています。
しかし、それは当たり前ですが無理なのです。。。
そこで、少しでもコンパクトカメラの弱点を減らし
コンパクトカメラにとって良い条件を与えてあげる事を考えたいと思います。
コンパクトカメラの弱点(1眼レフと比べても本当に仕方ない事ですが。。。)を敢えて言うならば
センサーの大きさ
測距の遅さ(ピント合わせが遅い)
高感度ノイズ
小型ストロボ(ストロボ光量)です。
では、実際に釣ってからリリースするまでの忙しい状況でどうやって弱点を減らすの?
と言う話だけしようと思います。
困っている方は参考にしてみて下さい(上手に撮れる方は ご自分の方法を崩さないで下さい)
1:測光とモード
モードはP(プログラム)
そして、測光を中央部重点測光にしてみて下さい。
下記写真の左から2つ目のマークが中央部重点測光です。
どのカメラも同じアイコンだと思います。
ここで「分け分からないなぁ〜。。。」となりがちですが、テレビのリモコン操作と同じす。
簡単なので操作してみて下さい。
測光とは、カメラが光を測る事。読んだままです。
カメラが光を計算する公式は3つあります。
評価測光(ファインダー全体の光量の平均を計算)
中央部重点測光(ファインダーの中央部分の光量を計算)
スポット測光(ピンポイントの光量を計算)
夜の撮影は必然的にファインダー内に黒が多く入ってきます。(バックが暗いから)
評価測光だと、ファインダー内の平均値を計算されてしまうので
黒が多ければ多い程
光の平均値は低くなるのでカメラはプログラムで強制的に明るくしようとします。
これによって、魚のディテールが白く飛んでしまうリスクがあります。
スポット測光だと測りたい場所を少し外した場合
白飛びしたり黒く潰れた写真になってしまうリスクがあります。
ややこしい測光パターンの話は ここまでにして
夜間のブツ持ち写真に関してファインダーの中央部に被写体が来る事が多いので
ファインダー中央部の光を重点的に測った方がリスクが少ないと思います。
2:ピント
まず、夜はピントもカメラにとって過酷になります。
そこで、、、
自分のヘッドライトと被写体となるアングラーの方がしているヘッドライト2つを使ってみましょう!
被写体となるアングラーの方もヘッドライトを外した方が様になりますし
撮影者側も補助光として2つのライトを使えるメリットは大きいです。
自分のヘッドライトはそのまま。
被写体の方から借りたライトを左手に持って(右利きの人)
サイドからライティングをプラスします。
この時、光量の多いライトをサイドから当てる様にして下さい。
撮影者のヘッドライトが明るい場合
ヘッドライトの位置を横へずらして被写体に当たる光量を落とします(和らげます)
そうすると光り物の反射も少なくなり、立体的なライティングになるのでカメラは測距しやすくなります。
必然的にピント精度が上がります。
撮影者から見て、被写体に当たるライティングが均等なら最高です。
魚への直接的なライティングは気をつけて下さい。
反射の激しい魚へライトを直接当ててしまうとカメラは明るいと状況を判断します。
そこで、反射の激しい魚でなく
魚から遠い位置にある人の顔へライティングします。
そうすると必然的に魚へのライティングは弱まり
補助光として柔らかいライティングが魚に当たる筈です。
補助光を上手く調整+ストロボ光で
全体的にバランスの取れたライティングにして下さい。
3:ストロボ調整
撮影したらモニターを確認しましょう。
暗ければストロボを+補正
明るければ−補正してストロボ光の調整をして下さい。
テレビのボリュームを上げ下げするのと同じ事なので簡単に出来ます。
下記のストロボ調整ボタンやモニター画面を見た事があると思いますが
それを+−すれば良いだけです。
4:確認作業
撮影後の確認作業は最も重要です!
パッと見はOKだったのに
帰宅してパソコンで見ると。。。
ピントが来てない。。。
ぶれている。。。。
なんて経験は誰でもあると思います。
そういう事を防ぐ為に再生する時は拡大して確認しましょう。
拡大してピントやブレを確認して下さい。
私も面倒な時に この作業を怠って痛い思いをした事が何度もあります。
せっかく魚と出会えたのだからキッチリ記録したいものです。
この1連の作業は慣れれば素早く出来ます。
そして、どうしても釣れない時は風景撮影も良いものです。
いつものフィールドを違った視点で見る事が出来ます。
斬新な感覚あり!釣りに関連した新しい発見あり!
良い気分転換になるので是非。
フィールド:小櫃川(千葉県)